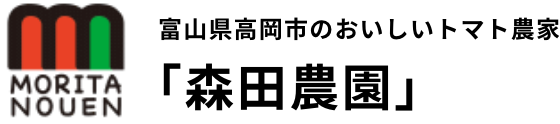THIS AND THAT OF TOMATO
トマトのあれこれ
長年トマトを栽培して思う事は、種を植え早く芽の出るもの、遅いもの、様々です。当然、早く芽の出たものは成長も早く、大きくなるのも早いです。また、最後まで元気に実をつけ終わるものや、途中で病気にかかり枯れてしまうもの、あげくの果てには、作業中に誤って茎を折ってしまう『事故』に遭遇するトマトなど、まるで人生の縮図を見ているようです。
トマトとの付き合いが長いと、そのルーツはどうなっているのか?どんな食べ方で、私たちの体にどう良いのか?いろいろ知りたくなります。そんなトマトに関するあれこれを少しご紹介します。
トマトのふるさと
トマトのふるさとは太陽の国アンデス。赤道に近いが山が高いので、昼間は暑くても夜はすずしく、雨が少なく空気が乾いている。そんな高原地帯が原産地です。
トマトは、トマト “tomato” なす科の果野類。ナスやピーマン、トウガラシ、ジャガイモなどは、遠い親戚にあたります。学名(栽培種)はLycoperslcon esculentum(リコペルシコン エスタレンタム)Lycosは「狼」、perslconは「桃」、esculentumは「食べられる」、つまり『食べられる桃』という意味だそうです。北海道のトマトジュースで『狼の桃』という商品名のものがありますが、この辺の由来を取ったのかも知れません。

トマトの日本伝来
徳川家綱のおかかえ画師だった狩野探幽の写生帳に『唐なすび』の絵が描かれており、<寛文8年(1668)写生>と記されているそうです。17世紀半ばごろまでには、日本に伝えられていたと思われ、最初は鑑賞用として珍重されたようです。
トマトが食用として利用される様になったのは明治以降だそうです。『西洋道中膝栗毛』で知られる仮名垣魯文 (ろぶん) が『西洋料理通』に蒸し赤ナス製法としてトマトの食べ方を紹介している。「赤ナスを細かく切って蒸し鍋に入れ、塩、こしょうを散らし静かに煮ること20分、酢をいれさらに5分煮る」と記した。この文献が日本のトマト食用利用第1号と思われるそうです。

おいしいトマト選びのポイント
ヘタが濃い緑色で枯れていないもの
全体の色が均一で皮に張りがあるもの
持って見てずしりと重たいもの(水に浮かべ沈むもの)
※カットした時、ゼリーが緑色のほうがおいしいです。

栽培途中で水を切ると
トマトはおいしくなる
植物(トマト)は、水が無いと生きてはいけません。そのため根の周りに水が少なくなると、トマトは生命の危機を感じ子孫(種)を残そうとします。種は、果実の中で果実内の栄養分を吸収し成熟しますが、トマトたちは危機感のある場合、今まで以上に果実内の栄養分を充実させようと努力します。結果として、美味しい果実が出来る事になります。

リコピンはカロチノイドの
ニューヒーロー
トマトに多くふくまれるリコピン。リコピンは、カロチノイドの仲間で、カロチノイドとは、植物などが作る黄色、橙、赤などの色素のことで、生活習慣病と闘って、酸化コレステロールを少なくしてくれます。どちらかと言えば、トマトを加熱調理した方が摂取されやすいようです。